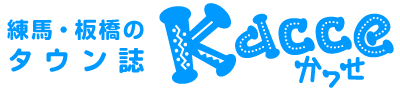※この投稿は、月刊Kacce2025年4月号(vol.493)掲載記事の再編集です。
お花見は、もともとは稲作の国・日本において稲の豊作を祈り、稲の神様と花の下で酒を飲み、ごちそうを食べるものでした。古代人は稲の神様のことを「サ」と呼んだと言われています。神様の食事を御食(みけ)といいますが、「ケ」は食事のことです。夕食を夕げというのは、「ケ」が「ゲ」になまったものです。サとケを合わせた「サケ(酒)」は神様の食事です。「御神酒あがらぬ神はなし」と言われ、儀式には欠かせないものになっています。桜のお花見が今のように庶民的になったのは江戸時代からで、ソメイヨシノが生まれたのもこの時代です。



散歩中、道端の斜面に密集していたのが、落葉つる性木本の「アケビ(木通・通草)」。名前の由来には、果実の色を表す“朱実(あけみ)”からという説や、果実が開く“開け実”からという説などがあります。
葉は掌状複葉で小葉は5個、雌雄同株です。花は淡紫色で花弁はなく、花弁状の3つの萼片(がくへん)があります。若葉の間から花序が垂れ下がり、先端に雄花が数個、基部側に雌花が1~3個つきます。雌花は直径3㎝位で、雄花はその半分程度の大きさです。花柄も雌花の方が長く、4㎝前後あります。雌花には円柱形の雌しべが5個前後、雄花には雄しべが6個あります。白花種のものは、シロバナアケビと呼ばれます。

白花といえば、「カラスノエンドウ」という呼び名が定着している標準和名「ヤハズエンドウ」の、まれに見る白花種・シロバナヤハズエンドウを道端で見かけました。
ゆっくりゆっくり春の散歩をお続けください。
森野かずみ